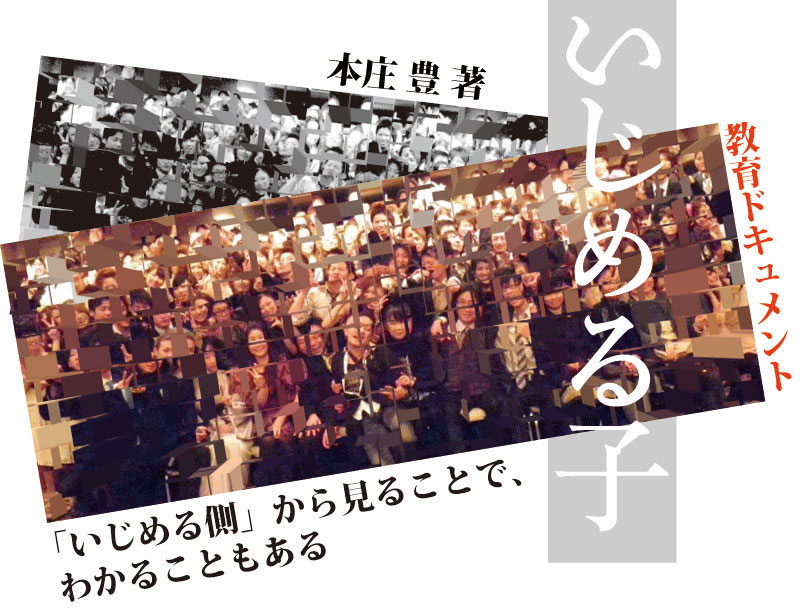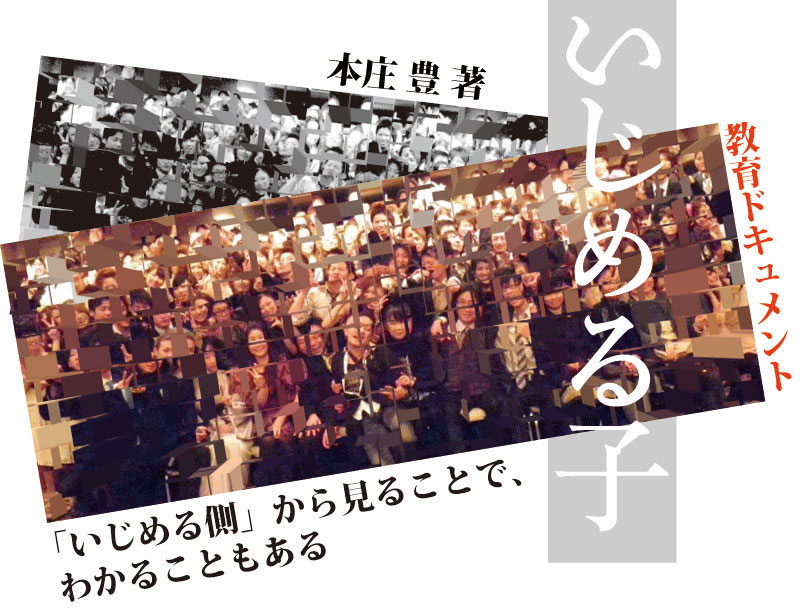本庄豊さんの『いじめる子』を新聞広告で見て、早速購入して読みました。
私も、地域高校・困難校といわれる高校での勤務が多かったため、悪戦苦闘したこと、失敗や未だに苦い想い出としてこびりついていること、 生徒と心が通じ合った時のことなどを思い浮かべながら、 一気に読み進みました。
本庄さんの教育実践の基盤にある、どの子にも惜しみなく注いでこられた愛情とパッションを 感じました。
本庄さんが、本のタイトルを「いじめる子」とされたように、いじめられる側からばかりでなく、いじめる側の視点を重視されていることに全く同感で、いじめの構造を生み出している日本の社会構造に切り込まなければ、
いじめ問題を解決する糸口は見つからないと思います。
多くの皆さんにお薦めしたい素晴らしい教育実践記録をありがとうございました。 (長野県 高等学校教員Kさま)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「いじめる子」読みました。最初の方の「美香と雄太」のあたりは、この夏休み前に担任の手におえない両親の相手を一週間したときの状況とぴったり重なり、引き込まれるものがありました。理不尽な要求をしてくる保護者との対応 について、いまさらながら確信したこは、「事実の確認を積み上げること」に尽きるということです。
この本のなかの管理職のように「言うことを聞いて、非を認めてあやまればいい」という態度では解決には向かいません。今は、こういうことをあらためて確認させてくれた保護者に一定の感謝をしています。(香川の中学校教員さま)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『いじめる子』読み終わりました。
読み始めたら止まらなくて一気に読破。
前半の中学時代の話しにも引き込まれましたが、後半、彼らが大人になってからの話しが圧巻。
『いじめ』そのもの、その時だけの捉え方だけでなく、その後の人生、成長、苦悩、歩みを知ることで社会との関わりが『いじめ問題』に深く関係していることに気づきました。
たくさんの人に読んでもらいたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二度目を読み終わり、一度目より更に深く考えるようになりました。
今『いじめ』に苦しんでいる子にも読んでもらいたいし、『いじめ問題』に直面している大人にも読んでもらいたい。
確かに『いじめ』はいけないことだしあってはならないけれど、私の息子をいじめていた子とその親とは今では仲良くなっています。息子をいじめていた当時は敵だったけれど……ね。
娘がいじめをしていると感じた時は何のためらいもなく担任に『いじめをしているようだ』と電話をし、関わっているすべての子とその親を集めてもらいました。
クラスでも話し合いをしてもらい、自分たちのしていることがいかに卑劣な行為であるかクラスメートから意見されることで身にしみて感じてもらいました。
中学で娘が人間関係で学校に行けなくなった時は『逃げることも必要』と学校を休むのを黙認しました。
私なりに子ども達に寄り添い続けた日々でした。
あとがきの中にある『弱者が自分より弱い立場の者に攻撃の矛先をむけている』という現実社会を変えていく以外に『いじめ問題』を解決する方法はないのかもしれないと感じます。
私たちにできることは何でしょう?
すぐに社会を変えることはできないかもしれないけれど『目の前にいる一人』の想いを受け止め、関わっていくことで少しでもいい方向になれば、と思います。
この本が光になることを願っています。 |